新NISAとは?新NISAのメリット・デメリットをわかりやすく解説!
本記事は、SBI新生銀行からのお知らせです。

2024年1月からスタートした「新NISA」は、初心者でも始めやすい資産運用といわれています。しかし、利用したことがないと、どのような投資手法なのかよくわからない場合もあるでしょう。
そこで、これから投資を始めたい人のために、新NISAの概要や、メリット・デメリット、実際に始める方法まで解説します。
目次
-
1.新NISA制度をわかりやすく解説
2.新NISAのメリット
2-1.制度が恒久化された
2-2.非課税での保有期間が無期限になった
2-3.「成長投資枠」と「つみたて投資枠」へと変更
2-4.年間の投資上限額が増えた
2-5.生涯非課税限度額が新設
2-6.売却すると非課税投資枠が復活する
3.新NISAのデメリット
3-1.旧NISAからの資産を移管できない
3-2.元本割れの可能性がある
3-3.対象商品が限定されている
3-4.損益通算ができない
3-5.繰越控除ができない
3-6.未成年は利用できない
4.新NISAに向いている人
5.新NISA(つみたて投資枠)の始め方
5-1.①NISA口座を開設する金融機関を決め、口座開設する
5-2.②積立金額を決め、口座に入金する
5-3.③金融商品を選ぶ
6.新NISAを始めるならクレカ積立がお得!
7.新NISAは手軽に長期・積立・分散ができる投資手法
新NISA制度をわかりやすく解説
NISAとは、2014年にできた少額投資非課税制度の愛称で、株式や投資信託への投資で得た利益に課税される税金が非課税になる制度です。
2024年には大幅にリニューアルされて「新NISA」と言われるようになりましたが、制度の本質は変わっていません。わかりやすく一言でいえば、新NISAとは、「投資で得た利益が非課税なので、効率的に資産運用ができる制度」です!
通常、投資を行った場合は、運用利益に対して20.315%(所得税15.315%と住民税5%)の税金がかかります。これは、売買益と配当金、どちらにもかかるお金です。つまり、投資で100万円の利益を得ても、実際に受け取れる金額は80万円弱になってしまうということです。
しかし、NISAを利用すれば非課税になります。つまり、100万円をそのまま受け取れるということです。これが、NISA制度の基本的なメリットとなります。
| NISA以外の口座 (税率20.315%) |
NISA口座 (非課税) |
|
|---|---|---|
| 資産運用の利益 | 100万円 | 100万円 |
| 発生する税金 | 約20万円 | 0円 |
| 実際の手取り金額 | 約80万円 | 100万円 |
新NISAのメリット
新NISAには、以前のNISAに比べてさまざまなメリットがあります。ここでは、そのうちの6つをご紹介します。
制度が恒久化された
旧NISAは新規口座の開設や運用できる期間が限定されていましたが、新NISAになり、制度が恒久化されました。つまり、「いつでも始めることができ、いつまでも使うことができる制度になった」ということです。
非課税での保有期間が無期限になった
旧NISAでは、非課税で保有(=運用)できる期間は5年か20年間と限定されていました。それに対して、新NISAは非課税での保有期間が無期限になりました。いつ始めても、一生涯、株式や投資信託を非課税で運用できるということです。
| 2023年まで | 2024年以降 | ||
|---|---|---|---|
| 制度の種類 | 一般NISA | つみたてNISA | 新NISA |
| 非課税保有期間 | 5年間 | 20年間 | 無期限 |
「成長投資枠」と「つみたて投資枠」へと変更
旧NISAから新NISAになり、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」ができました。旧つみたてNISAがつみたて投資枠に、旧一般NISAが成長投資枠に変わったイメージです。この2つは、対象となる投資商品が異なります。
一般NISAとつみたてNISAは併用ができませんでしたが、つみたて投資枠と成長投資枠は両方同時に使うことができます。そのため、自分が投資したい投資商品の種類に合わせて、どちらか好きなほうだけ、または両方を利用できます。
| つみたて投資枠 (旧つみたてNISAと類似) |
成長投資枠 (旧一般NISAと類似) |
|---|---|
| ・長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託 (金融庁の基準を満たしたものに限る) |
・上場株式 (整理・監理銘柄を除く) ・投資信託等 (信託期間20年未満、毎月分配型の投資信託およびデリバティブ取引を用いた一定のものを除く) |
年間の投資上限額が増えた
NISAでは、年間の投資上限額が限定されています。旧つみたてNISAは年間40万円、旧一般NISAは年間120万円まででしたが、新NISAでは最大で年間360万円まで投資をすることができます。
| つみたて投資枠 | 成長投資枠 |
|---|---|
| 年間120万円まで | 年間240万円まで |
| 併用すると合計で年間360万円 | |
生涯非課税限度額が新設
新NISAでは、年間の投資上限額が増えた代わりに、「生涯非課税限度額」が新設されました。生涯非課税限度額とは、生涯において非課税で保有できる限度額のことです。買付金額ベースで合計1,800万円となっています。なお、成長投資枠だけを使う場合は、生涯非課税限度額が1,200万円までとなります。
例えば、年間の投資上限額である360万円を毎年投資していくと、5年間で生涯非課税限度額に到達します。すると、NISA口座ではそれ以上商品を買うことができなくなります。
売却すると非課税投資枠が復活する
年間の投資上限額や生涯非課税限度額があるものの、新NISAでは、「売却したら非課税投資枠が復活する」という仕組みも新設されました。
具体的には、NISA口座で保有している商品を売却すると、売却をした商品を買ったときの金額分の生涯非課税限度額が、売却をした翌年に復活します。
つまり、生涯非課税限度額を使い切ったとしても、売却して翌年になれば、復活した枠を再利用して新NISAで新たに商品を買うことができるのです。これにより、保有商品の買い替えがしやすくなりました。
新NISAのデメリット
メリットが多い新NISAですが、利用する際にはデメリットも意識する必要があります。
旧NISAからの資産を移管できない
すでに旧NISAを使っていて、商品を保有している人もいるでしょう。旧NISAで保有している商品は、新NISAへの移管(ロールオーバー)ができません。そのため、旧NISAで保有している商品は、旧NISAの非課税保有期間が終わるタイミングで、「課税口座に移す」または「売る」必要があります。
旧NISAで保有している分は、新NISAの生涯非課税限度額とは別枠で、旧NISAの非課税保有期間が終わるまで非課税で運用ができます。それなので、旧NISAから新NISAへ急いで移管する必要性は特にないのではないでしょうか。
元本割れの可能性がある
運用利益が非課税であるNISAは、効率的に資産形成をするのに役立ちます。しかし、購入するのが投資商品である以上、元本割れの可能性があることを忘れてはいけません。
売却のタイミングや選んだ商品によっては、投資した金額よりも受け取れる金額が少なくなり、損をしてしまうこともあり得るのです。そのため、絶対にリスクを取れない資金については、NISAでの運用は避けたほうが無難と言えるでしょう。
対象商品が限定されている
新NISAでは、つみたて投資枠と成長投資枠でそれぞれ対象商品が限定されています。NISAの対象商品は株式や投資信託が対象のため、個別の債券や不動産、外貨預金などの投資をしたいときには、NISAを使えません。なかでもつみたて投資枠は、金融庁の基準を満たした一定の商品に限定されているため、色々な商品に投資したい人にはデメリットと言えるでしょう。
とはいえ、「数多くの商品から自分が買う商品を絞るのが大変」と感じる初心者にとっては、対象商品数が絞られていることは、むしろメリットと捉えられるかもしれません。
損益通算ができない
新NISAには、ほかの投資口座との損益通算ができないというデメリットがあります。
例えば、NISA口座内で買った商品を売って1万円の損失が発生した人が、同じ年に、別の投資口座で1万円の利益を出したとします。この場合、投資益はプラスマイナスでゼロですが、NISAは損益通算ができないため、別の投資口座で得た1万円の利益に対して課税されることになります。
つまり、NISA口座以外でも株式や投資信託の投資をしたい人は、NISAの使い方に注意が必要です。反対に、NISA口座内だけで投資をする場合には関係ないので、デメリットとはなりません。
繰越控除ができない
繰越控除ができない点も、NISA制度のデメリットです。株式等の繰越控除は、株や投資信託を売って発生した損失について、3年間繰り越して利益と相殺できる制度です。これがNISAでは利用できません。
ただし、繰越控除は、株式や投資信託で課税対象となる譲渡益や配当利益が出たときに使える制度です。課税対象となる利益が発生しないと繰越控除を使う条件はそろわないため、NISA口座以外で投資をしない人にとっては関係ありません。
未成年は利用できない
新NISAの対象年齢は「18歳以上」となっているため、その年の1月1日時点で18歳になっていない人は利用することができません。
18歳未満の子ども名義で非課税の投資ができる「ジュニアNISA」は、2024年に廃止されました。子どもの教育資金などをジュニアNISA口座でコツコツ貯めていた人は、今後は大人名義の新NISAの口座に貯めていくことも考えましょう。
目的が「子ども名義で貯めたい」「子どもに投資を教えたい」という場合は、子ども名義の課税口座(未成年口座)を利用することを検討すると良いでしょう。
新NISAに向いている人
新NISAのメリット・デメリットを踏まえると、次のような人に向いていると言えます。
<新NISAに向いている人>
・運用利益にかかる税金をなくして、効率よく資産運用をしたい人
・新NISAの対象となる株式や投資信託に投資したい人
・投資額が合計1,800万円未満(かつ年間投資額が360万円未満)の人
一方で、元本割れのリスクを避けたい人や、株式や投資信託以外に投資したい人には向いていません。
また、投資したい金額が新NISAの生涯非課税限度額である1,800万円を超える人は、NISA口座は活用しつつも、通常の課税口座の活用や、ほかの金融商品での資産運用も検討すると良いでしょう。その際、新NISA口座は損益通算や繰越控除を使えない点にご注意ください。
新NISA(つみたて投資枠)の始め方
新NISAは、次の3ステップで始めることができます。ここでは、初心者でも長期・積立・分散投資がしやすい「つみたて投資枠」を証券会社で始める場合を紹介します。
1. NISA口座を開設する金融機関を決め、口座開設する
新NISAを始めるためには、証券会社などでNISA口座を開設する必要があります。NISAは、すべての金融機関を通して1人1口座しか開設できません。金融機関によって取り扱っている商品や、最低積立金額は異なりますから、自分がどのように投資したいか考えて選びましょう。
NISA口座だけを単独で開設することはできず、「証券総合口座」または「投資信託口座」を開設していることが前提です。証券総合口座・投資信託口座には「一般口座」と「特定口座」があり、特定口座はさらに「源泉徴収あり」「源泉徴収なし」に分かれます。源泉徴収ありの特定口座なら、利用に応じて金融機関が自動的に税金を徴収してくれますから、確定申告の必要がなく、初心者におすすめです。
2. 積立金額を決め、口座に入金する
証券口座には、取引に利用するお金を入金します。入金は、銀行口座などからの振り込むことが可能です。なお、入金時の振込手数料は、金融機関により異なるため、事前に確認するようにしましょう。
つみたて投資枠の場合は、金融商品を積み立てる頻度と、いくらずつ積み立てるのかを決めることができます。例えば、「毎月1日に投資信託Aを500円分、投資信託Bを1,000円分」といった具合です。毎月ではなく、毎日積み立てることが可能な金融機関もあります。つみたて投資枠の年間投資上限額は120万円(12カ月で割るとひと月10万円)ですから、それに合わせて月々積み立てる金額を決めましょう。
3. 金融商品を選ぶ
購入する金融商品を選びます。つみたて投資枠の場合、購入できるのは手数料が一定以下の投資信託や、一部のETF(上場投資信託)のみに限られています。投資先(国や地域、株式のみ、株式と債券の両方を含むものなど)や、投資商品の基準価額の推移、純資産総額などを参考に、商品を選びましょう。
注文を確定したら、つみたて投資枠の設定は終了です。あとは、決めた頻度ごとに定期的に金融商品の買い付けが行われます。NISA口座で購入した商品は、自分の好きなタイミングで売却することができますし、途中で積立をやめることもできます。
新NISAを始めるならクレカ積立がお得!
新NISAを始める金融機関をどこにするかで迷ったら、「クレカ積立」の内容で決めるのもひとつの手です。クレカ積立とは、クレジットカード払いで定期的に投資信託などを購入する投資方法です。
クレカ積立の魅力は、クレジットカードのポイントが貯まるところです。金融機関によって使えるクレジットカードや還元率は異なりますが、投資額の1%前後のポイントが得られたりします。例えば、「月5万円クレカ払いで積立投資をしたら、毎月500ポイントもらえる」といったイメージです。
資産運用で利益が出るかは相場にもよりますが、クレカ積立によるポイントは相場に関係なく貯めることができます。そのため、積立投資をするのであれば、クレカ積立ができる“おまけ”がついてくる金融機関でNISA口座を開設するとお得と言えます。
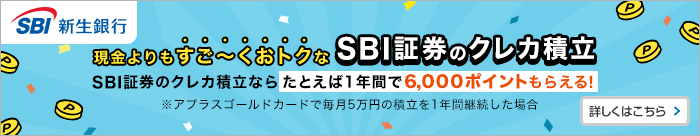
新NISAは手軽に長期・積立・分散ができる投資手法
投資の利益が非課税になる新NISAは、個人投資家ならぜひ活用して欲しい制度です。
なかでも、つみたて投資枠では長期・積立・分散という3つの特徴を兼ね備えた資産形成ができるため、初心者にもおすすめです。NISAとクレカ積立を併用すれば、より効率よく資産を増やしやすくなります。
これから投資を始める人や、長期的に安定した資産形成がしたい人は、ぜひ活用しましょう!
\ ネットでカンタン口座開設 /
SBI新生銀行で今すぐ口座開設



 ポスト
ポスト シェア
シェア LINEで送る
LINEで送る
