50代におすすめ!老後のための資産運用とは?
本記事は、SBI新生銀行からのお知らせです。

50代は子どもが手を離れ、定年退職のカウントダウンも始まる年代。老後資金が思ったほど溜まっていない、人生100年時代を生き抜くための資金は足りるのだろうか?と不安を募らせる方も多くいらっしゃいます。そんな50代のみなさんに今回は老後に向けた資産運用、という視点でお話しようと思います。
目次
50代に資産運用は必要か?
「50代に資産運用は必要か?」の問いの答えはもちろん「イエス」です。それは以下の理由から考えられます。
8割以上の人が老後資金に不安を抱えている!
生命保険文化センターの「2022(令和4)年度 生活保障に関する調査」によると調査対象の8割以上の人は、老後生活に対する不安を持っているそうです。(※)
(※)生命保険文化センター 2022(令和4)年度 生活保障に関する調査
さらに、同資料を見ると、公的年金だけでは不十分であることが、不安の理由のトップであることがわかりました。
総務省統計局発表の家計調査報告によると、65歳以上の夫婦高齢者無職世帯の収入のうち、公的年金等にあたる「社会保障給付」の額は、2022年の平均で220,418円となっています。
年金の受給額は、働き方や、働いた期間、お給料の額などで、それぞれ異なります。
統計数字を基にした収支計算の例は後述しますが、上記の統計数字としての年金額(社会保障給付)を見るだけでも、年金だけで贅沢な暮らしが送れるわけではないことは容易に想像がつきます。
また、令和3年の厚生労働省「簡易生命表」によると、日本人の男性の平均寿命は81.47歳、女性の平均寿命は87.57歳です。昭和22年の平均寿命は男性50.06歳、女性は53.96歳でしたので、約70年間で、日本人は30年以上長生きできるようになったことになります。寿命が延びたことで、ライフスタイルも大きく変わりました。長生きリスクとして挙げられるのは、病気や介護。生命保険文化センターが2021年に行った調査によると、1人あたりの介護費用は月平均で8.3万円かかると言われています。
人生100年時代といわれる昨今では、老後のための資産作りは、1つの命題だといえそうです。長生きリスクのほかインフレについても不安を抱える方が少なくありません。9月の消費者物価指数(生鮮食品を除く)は前年同月比2.8%(2023年10月20日総務省による)でした。インフレにも対応できるよう預貯金だけでなく資産運用を視野にいれることは大切だといえるでしょう。
50代時点で定める将来の金融資産の目標金額
50代時点で定める将来のための金融資産の目標額は、最低でも老後生活における収支の不足額をカバーできる金額に設定すると良いでしょう。
たとえば、先述した総務省統計局の家計調査報告によると、65歳以上の夫婦高齢者無職世帯の家計収支は、2022年の平均で下記のとおりになっています。
| 項目 | 金額 | |
|---|---|---|
| 実収入 | 246,237円 | |
| 支出 | 非消費支出 | 31,812円 |
| 消費支出 | 236,696円 | |
| 不足分 | 22,270円 | |
ここでいう実収入には、公的年金等(社会保障給付)以外の収入も入っています。仮に、65歳から90歳までの25年間で、毎月22,270円が不足するとしたら、不足額の総額は、668万円という結果になります。
ただこれはあくまでも、平均的な金額です。長生きをすればそれだけ不足額の総額は大きくなりますし、生活水準が高い方は、家計調査の例より支出額が大きくなると思われます。老後の年数と毎月の不足額を基に不足額の総額を表にしたものを下記に作成しました。
| 老後の年数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25年 | 30年 | 35年 | ||
| 毎月の不足額 | 20,000円 | 6,000,000 | 7,200,000 | 8,400,000 |
| 40,000円 | 12,000,000 | 14,400,000 | 16,800,000 | |
| 60,000円 | 18,000,000 | 21,600,000 | 25,200,000 | |
このように計算した老後生活期間における不足額の総額が、最低限リタイアまでに作っておいた方が良い金融資産の目標額となります。
生活費の計算方法
生活費の計算は、統計数字だけでは心許ないため、自身の家計に基づいて計算してみましょう。
老後の生活費を計算する前に、今の生活費を確認し、そこから老後にかかりそうな生活費を推測してみると良いでしょう。今の生活費を正確に把握するには、やはり家計簿が1番。最近では、パソコンやスマートフォンのアプリで簡単に家計簿をつけることができます。クレジットカードの決済は引き落とし先の銀行口座を登録、現金での決済はレシートを撮影するだけで、おおよその支出が確認できます。
今の支出を把握できれば、そこから退職後には必要がなくなりそうな出費を差し引きましょう。たとえば、ランチを外食ですませている方は、退職すると食費は減りますよね。スーツやシャツなどの服飾費用も減るのではないでしょうか。また、子どもが独立して生活をはじめれば、多額の死亡保険金をのこすような生命保険などは必要なくなるかもしれません。
このように、退職後の月々の生活費を大まかに知ることが、最初の一歩です。
退職までに用意しなければならないお金の額は、その後どういう暮らし方をしたいのか?によって、人それぞれ異なります。 たとえば生命保険文化センターの調査で「ゆとりある老後生活のために必要な生活費は夫婦で月額37.9万円」というデータがあります(※)。先述の家計調査の毎月の消費支出額(約24万円)より大分大きな金額であり、生活水準によって、支出額は大きく異なることがわかります。
(※)生命保険文化センター2022(令和4)年度 生活保障に関する調査参照
50代の実際の資産状況と資産運用の必要性
「50代の時点で、どのくらいの資産を持っていたほうがいいの?」という疑問をお持ちの人は多いと思います。総務省統計局の「家計調査報告(貯蓄・負債編)―2022年(令和4年)平均結果―(二人以上の世帯)」によると、2022年時点の年代別の貯蓄現在高は下記のとおりになっています。
| 40歳未満 | 40~49歳 | 50〜59歳 | 60〜69歳 | 70歳以上 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 貯蓄現在高 | 812万円 | 1,160万円 | 1,828万円 | 2,458万円 | 2,411万円 |
(出典)総務省統計局「家計調査報告(貯蓄・負債編)―2022年(令和4年)平均結果―(二人以上の世帯)」より筆者作成
自身の貯蓄高が平均より高いからといって油断はできません。先述のとおり、老後に必要な金額は個々に異なるからです。平均よりも貯蓄高が少ない人は不安に思うかもしれませんが、十分にキャッチアップは可能です。たとえば、退職金を受け取ることで、60代に金融資産が一気に増加する人は少なくありません。
また、仮に年間に100万円の貯蓄ができれば、10年で1,000万円の貯蓄増が見込めます。「平均額以上の貯蓄高は目指したい」という人は、今からできることに注力をすることが大切です。
また、ただ貯蓄を続けるだけでなく、資産運用をすることも大切です。たとえば、50歳時点で1,000万円の貯蓄残高がある人が、70歳時点で資産を1,400万円増加させ、70歳以上の平均的な貯蓄高(約2,400万円)を目指すとしたら、運用をする場合としない場合で、必要となる毎月の積立額は異なります。下記は、運用をしないケースと年3%の運用益が得られるケース、年5%の運用益が得られるケースで、20年で1,400万円を作るために必要な毎月の積立額を表にしたものです。
| 運用しない場合 | 年3%で運用できた場合 | 年5%で運用できた場合 |
|---|---|---|
| 58,333円 | 42,600円 | 33,900円 |
この表から、同じ目標額を作るにしても、資産運用をするのとしないのでは、必要な金額が大きく異なることがわかります。「これまで積極的に資産形成をしてこなかった」という人ほど、これからのことを考えることが大切です。
50代が毎月の収入から資産運用に回す割合
ここまでの解説のとおり、毎月の収入から資産運用に回すべき金額は、目標金額や現時点の貯蓄高、資産運用をするのかしないのかによって異なります。もし、このような逆算的な考え方が苦手な人は、「収入の1割以上」といったわかりやすいルールを作るのも一案です。あるいは、今まで教育費に使っていたお金が、子どもが社会人になったことで浮いている場合、その金額をそのまま資産運用にまわす方法もあるかと思います。この方法は生活水準を下げずに、無理なく老後資金を貯める方法です。大切なことは、継続的に貯蓄残高が増えるルール作りをすることです。
50代におすすめの資産運用
資産運用の初心者に向いているのが、投資信託です。投資信託は、運用の専門家が投資家に代わって株や債券を複数種類選択してくれる便利な投資商品です。自身で株や債券を選べないという人でも、自身の運用方針に合った投資信託を選ぶことでしっかりと運用をすることができます。ただし、元本割れのリスク、手数料がかかる旨は理解しておく必要があります。これらの留意点については、各金融機関の商品説明書に記載されています。
投資に苦手意識がある人は、貯蓄性の高い個人年金保険や外貨を含めた定期預金などを検討するのも一案です。念の為、外貨系の商品は為替変動リスクや円でのお預け入れ・お引き出しなど通貨の交換には所定の為替手数料がかかることにも注意が必要です。
関連記事:外貨預金とは?その仕組みから始め方を解説
50代が資産運用に活用したい制度
投資信託で運用する際には、まずは「個人型確定拠出年金(iDeCo)」や「少額投資非課税制度(NISA・つみたてNISA)」を利用することから考えると良いでしょう。これらの制度は運用益に対する税金がかからないため、より効率的に資産形成ができるからです。
iDeCoについては「50代から年金の新しい制度を始めるのは遅いかも・・」という声を聞くことがありますが、そのように考える必要はありません。2022年5月からはiDeCo加入年齢が5年延び、65歳になるまで積み立てが可能となりました。また、受給開始年齢が最長で75歳になったため、iDeCoは65歳以降も一定期間運用し続けることができます。50代から70代にかけては10〜20年程度の年数があり、十分な運用期間が確保されているといえます。
2024年1月から始まる新しいNISAにおいて「つみたて投資枠」では年120万円、「成長投資枠」では年240万円の非課税投資枠が設けられています。非課税で運用できる期間は恒久化されるため、自分のペースで長期的な資産形成を計ることができます。
投資信託を一定期間ごとに同じ金額ずつ購入する「つみたて投資枠」で購入できる投資信託は、長期・積立・分散投資に適した商品が厳選されています。価格のブレを抑えながら効率よく資産形成することが期待できます。
なお、NISAによる資産形成は、給与自動引落や口座振替だけでなくクレカ積立で利用することも可能です。
クレカ積立とは、クレジットカードを利用して投資信託や株式の積立投資を行うサービスです。クレカ積立は、2018年に始まりここ数年でクレジットカード会社と証券会社が提携しサービスを開始する企業が増えています。
クレジットカードを投資の決済に利用するには、毎月一定額を継続的に購入する積立、翌月の一括払いなどの条件を満たし利用できるようになっています。
自分が選んだ投資信託を自動的に決まった日にクレジットカード払いで購入します。1度積立の設定をすれば、定期的に商品が購入されていき、ほかのショッピング代金と一緒に積立金額がカード口座から引き落とされます。
クレジットカードの多くは、利用額に応じてポイントが還元されます。つみたてNISAに利用した場合も同様に、長期間継続して投資しクレジットカード決済を続けることで、多くのポイントを得ることができます。
クレカ積立を始める際は、各証券会社で使えるクレジットカードの種類、取扱っている投資信託、積立額に対するポイント還元率などを確認してみてください。
関連記事:つみたてNISAは何がお得?始め方やメリットを解説
50代が資産運用で避けたい行動
インターネット等で検索すると流行りの投資方法が出てくると思います。リスクが高いものへの投資は最もしてはならない投資方法です。老後資金を増やすための行動として行ってはならないものは、レバレッジ型のハイリスクな投資信託、株式の信用取引などがあげられます。これらは、投資というよりは投機といわれており、ギャンブル性が高いため、着実な資産形成を目指したい人には向かない商品だといえます。
老後の資産運用として、退職金で運用するという選択肢も!
退職金の運用方法は多くの人が悩みます。預貯金、個人向け国債、投資信託、ETF(上場連動信託)など、さまざまな選択肢がありますが、どういった商品を選ぶかは、それまでの運用経験が大きく影響します。退職金を受け取るまでに、運用経験を積んでおくと、選択肢を広げることができます。また、ひとつの方法に絞るのではなく、様々な商品を組み合わせたポートフォリオ(資産の組み合わせ)で長期的に分散し、低コストの運用を目指すのが基本になります。
おすすめの退職金運用法
退職金を運用する際には、まずは使用予定資金と余剰資金に分け、余剰資金部分を運用する、という考え方が大切です。投資信託で運用しながら、徐々に取り崩す方法や、高配当株や債券を購入して配当や金利を不労所得にするという方法もあります。繰り返しになりますが、選択肢を広げるために、50代のうちに運用の経験値を積んでおくことが大切です。
もちろんひとりで考えるだけでなく、銀行の窓口にいる信頼できる投資運用のプロに相談することもリスク回避の方法となります。大事な退職金を上手に運用できるようにプロの知恵を借りることも視野に入れましょう。
関連記事:退職金の安全な運用方法は?老後を安心して過ごすための資産づくり
老後の資産運用で注意すべき点
老後においては、自身の理解が及ばないハイリスクな商品には手を出さないことをおすすめします。退職金や、それまでに培った資産が大幅に目減りしてしまった際に、リカバリーをするのに時間がかかり、必要な時期に必要なお金が足りないという事態になり得るからです。たとえば、資産分散をせずにひとつの金融商品に1点集中投資をしてしまうこと、短期売買で大きな利益を得ようとすること、ハイリスクハイリターンの商品に投資することなどは特に避けた方が良い投資方法だといえます。また、定年間際は労働による収入を得られる期間が限られています。これは運用に振り向ける原資が限られていることを意味します。年齢を重ねるほど、保有資産を守る意識を持つことが大切です。
資産運用を長期でおこなうことで、明るく自分らしい人生を歩めるようにしよう
50代以降の資産運用は、老後の生活のイメージを具体的にし、必要な資産を着実に積み上げていく計画作りが大切になります。人生100年時代と言われており、長生きするほどお金が必要になることはいうまでもありません。ただ、人生の時間が延びるということは、資産運用を長期でおこなう機会でもあります。明るく自分らしい人生を歩めるよう、人生の棚卸し、老後の生活費の算出、各種制度のリサーチ、もらえる年金額など、一度しっかり向き合うことをおすすめします。
執筆者プロフィール


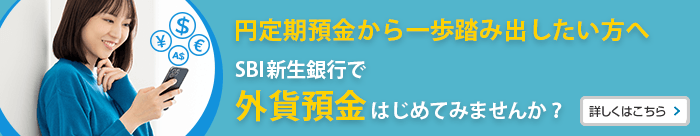
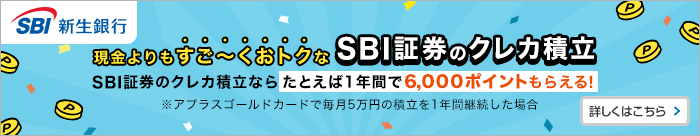
 ポスト
ポスト シェア
シェア LINEで送る
LINEで送る
