子ども名義の銀行口座は必要?開設のメリットや注意点を解説
本記事は、SBI新生銀行からのお知らせです。

子どもが生まれると、お祝い金や将来の教育資金など、子どものお金を管理する機会が増えてきます。そうした場合に備えて、用意しておきたいのが、子ども名義の銀行口座です。
「子ども名義の口座はいつ作ればいいの?」「税金はかからないの?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
本記事では、子ども名義の口座を作るメリットや注意点、必要な書類、手続きの流れ、税金対策までをわかりやすく解説します。
目次
子ども名義の口座は何歳から作ることができる?
子ども名義の口座は生まれてすぐの「0歳」から開設することができます。その場合、口座開設の手続きは、父母などの親権者が「法定代理人」として行う必要があります。
また、口座開設には子どもの住民票など、本人確認書類の提出が求められます。そのため、出産前に口座を開設することはできません。生まれてから必要書類が揃い次第、口座開設の準備を進めましょう。
近年は店頭での手続きだけではなく、スマートフォンやパソコンから申し込みができる銀行も増えており、忙しい育児の合間でも手軽に口座開設が可能になっています。
子ども名義の口座を開設するメリットとは?
親の口座を使って子どものお金を管理することもできますが、子ども自身の名義で口座を開設することで、教育資金の管理がしやすくなったり、お金の使い方を学ぶきっかけになったりと、得られるメリットは少なくありません。
ここでは子ども名義の口座を開設する4つのメリットをご紹介します。
1.教育資金を生活費と分けて管理できる
教育資金は、将来に向けて長期的に準備していく必要があります。そのため、普段使う生活費とは分けて管理したほうが安心です。子ども専用の口座を用意することで生活費の口座と明確に区別ができ、教育資金を計画的に貯めやすくなります。
例えば、毎月一定額を子ども名義の口座に積み立てておくことで、学費や塾代などが必要になったタイミングに合わせて、お金をスムーズに取り出すことができます。
また、生活費と混在させてしまうと、知らないうちに教育資金を取り崩してしまう可能性もあるため、口座を分けることはリスク管理の点でも非常に有効です。
2.お年玉やお小遣いの安全な管理ができる
子どもがもらったお年玉やお祝い金は、親が代わりに管理することが一般的です。とはいえ、自宅で現金のまま保管していると、紛失や盗難のリスクもあります。また、生活費と混在するとうっかり使ってしまう可能性もあります。
そんなときに子ども専用の口座を用意しておけば、こういったトラブルを防ぎながら、もらったお金をきちんと保管・管理することができます。
また、口座を分けておくことでお金の使い道が明確になり、親にとっても安心です。将来的には、子ども自身が「自分のお金」を意識するきっかけにもなり、金融教育にもつながります。
3.お金の出し入れが柔軟にできる
子どもの教育資金準備といえば学資保険を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。学資保険とは、子どもの進学や進級に合わせて保険金が受け取れる貯蓄型の保険で、計画的に教育資金を準備できるのが特徴です。
また、契約者に万が一のことがあった場合には、以後の保険料が免除される(払込免除)など保障機能がついている点もメリットです。
一方で、途中で解約すると元本割れを起こす可能性があることや、受け取り時期があらかじめ決まっているため、急な出費には対応しづらいという側面もあります。
その点、子ども名義の銀行口座であれば、入出金に制限がないため、必要に応じていつでも自由にお金を出し入れできます。思いがけない出費や、教育資金以外でお金が必要になった際には銀行であれば柔軟に対応できます。
4.子どもの金融教育につながる
子どもがある程度大きくなってきたら、自分の銀行口座を使ってお金を管理する練習をさせてみるのもおすすめです。例えば、貯めたお金をどう使うかを自分で考える経験を通して、「お金の価値」や「使い方の優先順位」などを自然に学んでいくことができます。
また、銀行に預けることで、手元で現金を持っているより安全に管理できることや、利息がつくといった仕組みに触れることもできます。これによって「お金をただ貯めるだけでなく、どう預けるかで変わる」という感覚も少しずつ育まれていきます。
実際に通帳を見せながら、「これは何のために貯めているのか」「いくら使うと残りはいくらになるのか」などを一緒に確認する時間は、親子のコミュニケーションにもなります。
将来、家計管理ができる大人に育てるための第一歩として、子ども名義の口座を活用してみてはいかがでしょうか?
子ども名義の口座を開設するときのデメリット・注意点
子ども名義の銀行口座を開設することには多くのメリットがありますが、注意しておきたい点もいくつかあります。開設後に「こんなはずではなかった」とならないように、事前に知っておきたいポイントを押さえておきましょう。
1.管理の手間が発生する
子ども名義の口座は、親が代わりに管理することになります。お子さんが2人以上いらっしゃったり、目的別に複数の口座を持っている場合は、それぞれの口座の残高を確認したり、使い分けたりする手間が増えていきます。
例えば、複数の口座から教育資金を支払う場合は、それぞれの口座で手続きが必要になり、1つの口座でまとめて管理するよりも負担が大きくなります。また、残高を把握していなければ、引き落とし時に残高不足になることもあるため注意が必要です。
こうしたトラブルを防ぐためにも、使い道や目的ごとにルールを決めておくと、無理なく管理しやすくなります。
2.子どもが成人したあとは本人しか手続きできない
子どもが成人するまでは、親が法定代理人として子ども名義の口座を管理することができます。しかし、18歳を迎えると原則として、子ども本人しか入出金や口座の解約などの手続きができなくなります。
そのため、例えば大学の入学金や授業料を子どもの口座から支払おうとした場合、親が単独で手続きすることはできず、子どもからの委任状が必要になるなど、本人に対応してもらう必要があります。
このような事態を避けるためにも、子ども自身に口座の管理を任せる場合は、どのように使っていくのか、親子でよく話し合っておくことが大切です。
進学や就職で忙しくなる時期を見据えて、18歳になる前に口座の管理方針を家族で確認しておきましょう。
3.10年間使用しないと「休眠預金」になる
使わないまま長期間(通常10年以上)放置された口座「休眠預金」とみなされ、預金保険機構を通じて公共目的に活用される場合があります。
手続きをすれば引き出すことも可能ですが、再度本人確認書類の提出が必要になるなど、手続きに時間がかかる場合もあります。子どもが小さいうちに作った口座は、親の意識からも薄れやすく、気づけば長年使っていなかったということも。
そうならないよう、定期的な残高の確認や少額でも入出金を行うなどして、休眠扱いにならないようにしておきましょう。
4.場合によっては贈与税がかかる
贈与税とは、個人から財産をもらったときにかかる税金です。1月1日から12月31日までの1年間に110万円を超える贈与を受けた場合、その超えた分に対して課税される仕組みになっています。
親子間であっても、110万円を超える金額を贈与すれば、基本的には贈与税の対象になります。ただし、生活費や教育資金として必要な範囲であれば、課税されません。
なお、贈与税には本人(または法定代理人)による申告義務があり、申告を怠った場合は無申告加算税などのペナルティが科されることもあります。具体的な対策や非課税制度の詳細は、後述の「教育資金を貯めるときの贈与税対策と非課税制度」でご紹介します。
子どもの口座開設に必要なもの・手続きの流れ
18歳以下の子どもの口座を開設する際に必要な書類と、手続きの流れをご説明します。銀行によって必要書類や手続きに違いはありますが、こちらではSBI新生銀行の未成年口座を例に挙げます。
≪口座開設に必要なもの≫
①捺印した申込書
②必要書類:法定代理人による取引の届出書または同意書
②本人確認書類:住民票の写しまたは戸籍謄本と附票
≪手続きの流れ≫
18歳未満の口座開設は、次の4ステップで完了します。
①スマホやパソコンから必要事項を入力
②申込書が自宅に郵送される
③捺印した申込書と必要書類・本人確認書類を返送
④キャッシュカードが届く
また、子どもの口座を開設するには、親権者のいずれかがSBI新生銀行で口座を持っていることが前提となります。
まだお持ちでない場合は、先に口座を開設しておきましょう。成人の口座開設はWebで簡単に手続きが完了するため、スムーズに準備することができます。
子どもの口座開設はSBI新生銀行の「U28」がおすすめ
SBI新生銀行は2024年12月より新しく「U28 Zero世代」というサービスを開始しました。28歳以下の方が対象で、口座を開設するだけでステップアッププログラムの最上位ステージである「ダイヤモンドステージ」に自動でランクアップされます。
手数料の優遇や金利の上乗せなど、さまざまな特典を受けられる点が大きな魅力です。
≪「U28」の主な特典(執筆時点:2025年8月現在)≫
・提携ATM出金手数料:何度でも0円
・他行宛てネット振込手数料:10回/月まで0円
・円普通預金金利:年0.40%(税引前、税引後 年 0.3187%。2025年8月1日現在)
子どものお金や教育資金などの日常的な資金管理はもちろん、長期的な貯蓄にも活用できます。さらに、スマホで残高の確認や振込操作も簡単にできるので、将来的に子どもが自分で管理するようになってからも使いやすいのがポイントです。
また、全国どこにいても利用できるパワーダイレクト(インターネットバンキング)に対応しているため、大学進学や就職、転勤などで地元を離れても、引き続き便利に使えるのも魅力です。
子どもが小さいうちに作った口座を、大人になってからもそのまま使い続けられる設計になっているため、成人後も長く安心して使える口座となっています。
教育資金を貯めるときの贈与税対策と非課税制度
子どもの教育資金を長期的に貯めていくうえで、気をつけたいのが「贈与税」です。一度にまとまった金額を子ども名義の口座に移すと、贈与税が課されてしまう場合があります。ここでは、基本的な贈与税対策と、教育資金に関する非課税制度をご紹介します。
1.贈与額を年間110万円以内に収める
贈与税には、年間110万円まで非課税となる「基礎控除」があります。1年間で子どもに渡す金額が、110万円以下であれば贈与税はかかりません。複数年にわたって贈与すれば、多くの教育資金を貯めていくことが可能になります。
2.贈与契約書を都度作成する
贈与は口頭での約束でも成立します。しかし、贈与契約書を作成して客観的な証拠を残すことで、税務上のトラブルを防ぐことができます。贈与のたびに簡単な贈与契約書を作成しておくのがおすすめです。
3.あえて贈与税を支払う
110万円を超える贈与であっても超えている部分が少額であれば税率も低く、課税額はあまり大きくありません。贈与税の申告をすれば税務署に記録が残るため、あえて贈与税を申告することで証拠を残すことも選択肢の一つとしてあります。
子どもの将来のために、メリット・注意点を理解して口座開設を
ここまで、子ども名義の銀行口座を開設するメリットや注意点について解説してきました。子ども名義の銀行口座を開設することは、生活費と分けて教育資金を管理できることに加え、子どもの成長にあわせて金銭感覚を養うツールとしても活用できます。
一方で、贈与税や管理の手間、成人したあとの対応など、注意すべき点もあります。制度や仕組みを正しく理解したうえで利用していきましょう。本記事が、子どもの将来を見据え、どのように銀行口座を活用していくかを考えるきっかけになれば幸いです。
よくある質問
Q: 子どもの名義でお預け入れをすると税金はかかりますか?
A: 年間110万円以内の贈与であれば、基礎控除の範囲内となり贈与税はかかりません。また、生活費や教育費の範囲であれば、通常は非課税とされます。ただし、事前に「一定期間・一定金額の贈与契約」がある場合は、「定期贈与」とみなされ、全体の金額に対して一括で贈与税が課される可能性があります。そのため「都度の贈与である」ことを明確にするためにも、贈与のたびに契約書を作成するなど、継続的な贈与の意思がないことを示す証拠を残しておくことが重要です。
Q: 子どもが大きくなったら口座はどうすればいいですか?
A: 18歳を迎えると、原則として親など本人以外による手続きができなくなります。自分で管理できる年齢になれば、家族で口座の使い方や管理方法について話し合い、通帳やキャッシュカードの保管・管理は本人に任せていくようにしましょう。
Q: 親以外(祖父母など)でも、子どもの口座を開設できますか?
A: 口座の開設には法定代理人(父母)である親権者の同意や手続きが必要です。父母が法定代理人である場合は、祖父母が口座開設をすることは原則としてできません。
Q: どのタイミングで子ども名義の口座を作るのがよいですか?
A: 出生届の提出後、健康保険証や住民票などが揃ったタイミングで作るのがおすすめです。お祝い金やお年玉、児童手当などを管理する際にも活用できます。
\ ネットでカンタン口座開設 /
SBI新生銀行で今すぐ口座開設

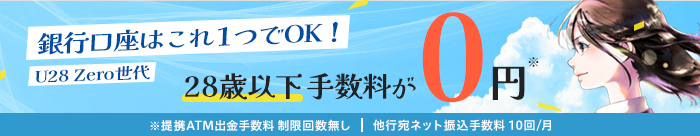

 ポスト
ポスト シェア
シェア LINEで送る
LINEで送る
