資産運用と投資の違いとは?資産形成のために知っておきたい知識
本記事はSBI新生銀行からのお知らせです。
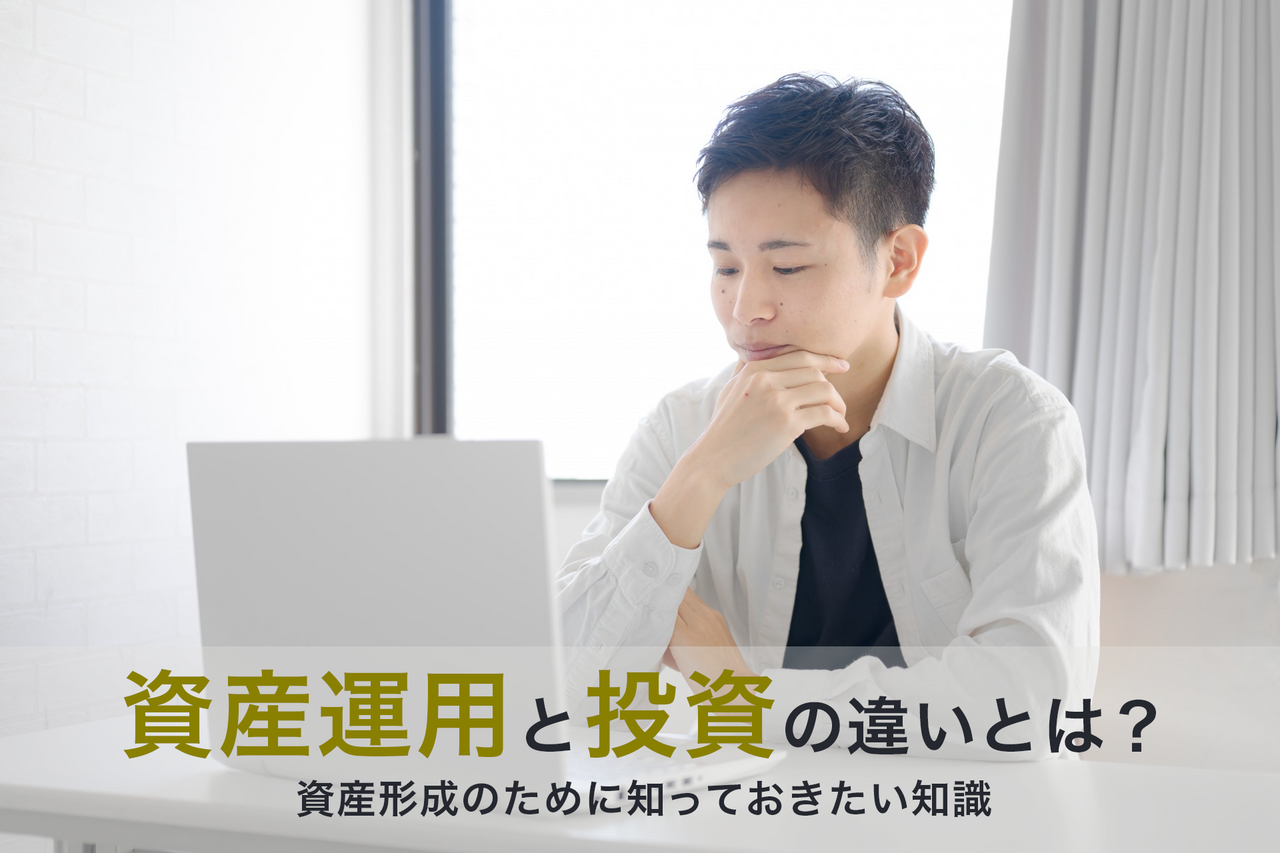
「資産運用」と「投資」について、違いをきちんと理解しているという方は、案外少ないのではないでしょうか。投資家の中にも、資産運用と投資を同じ意味合いで使っている人はたくさんいます。しかし、この2つの言葉は、まったく同じ意味ではありません。
資産運用と投資の言葉の意味の違いを知ることは、自分に合った資産運用や投資を始める一助になります。今回は、言葉の意味の違いのほか、資産運用のメリットやデメリット、始めるときの注意点についてご紹介します。
目次
資産運用と投資の違いとは?
資産運用と投資は、そもそも、同じレベルに存在する言葉ではありません。資産運用の手段のひとつが投資であり、両者を明確に分ける基準があるわけではありません。
例えばリンゴとブドウは両方ともフルーツの名前ですが、フルーツとリンゴは、そもそものカテゴリが違います。資産運用と投資もこれと同様です。両者の具体的な意味について見てみましょう。
資産運用とは?
資産運用とは、自分が持っている資産を活用して利益を得たり、資産を増やしたりすることを幅広く指します。
資産運用のための手段はさまざまですが、お金を預けることで利息がもらえる銀行預金のような安全性の高い方法から、日々価格が変動して損益が出る株式や債券などの方法まで含みます。
つまり、資産運用とは、今ある自分の資産を「リスクをとって運用する部分」と、「リスクを取らずに円の預貯金などで確実に置いておくもの」とに分け、全体として効率的な置き方にすることを指すのです。そのため、自分の資産を、いつ・いくら使うのかなども意識しながら、具体的な資産運用方法を決めていくことが重要となります。
投資とは?
一方で投資とは、資金を金融商品などに投じることで、利益を期待するものです。投資は資産運用の一部ですが、資産運用と異なり、元本保証のある銀行預金などは除かれます。「利益を得ること」に重点を置くものに限定しているとイメージすると良いでしょう。
投資と呼ばれるときの具体的な運用方法としては、株式投資や債券投資、外貨預金、不動産投資、投資信託などが挙げられます。
例えば株式を購入した場合は、株価が大きく上昇したときに売却すれば、大きなリターンが得られます。しかし、株価が下落すれば、株式の価値は取得したときより下がってしまう元本割れのリスクがあります。そのため、利益が出そうな株式を見極めて資金を投じることが重要となります。
なお、利益が出るかどうかを運任せや神頼みにして金融商品にお金を投じる場合は、「投機」と言われて投資と区別されたり、ギャンブルと同義に扱われることもあります。これは資産運用とは言い難いので、このような買い方は避けるようにしてください。
つまり、100万円が手元にあったとき、これを全体的に預貯金と投資資金に分けて運用して110万円にしようというのが資産運用で、100万円のうち10万円(=リスクを取っても良い金額)を投資資金として資産が増えそうな金融商品に投じてリターンを得ようという部分が投資なのです。
資産運用のメリット・デメリットとは?
資産運用と投資の意味の違いがわかったところで、資産運用のメリットやデメリットについても確認しておきましょう。
資産運用のメリット
資産運用のメリットは、一言でいえば「資産を効率よく増やせる可能性がある」ことです。資産運用をしない場合とした場合でシミュレーションしてみましょう。
例えば、「老後を安心して暮らすために、65歳までに2,000万円を目標に貯めたい」と考えている45歳の人がいるとします。資産運用せずにただ現金をタンスに貯めていく場合、目標を達成するためには、65歳までの20年間、毎年100万円を貯めていかなくてはいけません。ひと月当たりでは、約8.3万円です。日々色々な出費が発生する中で、毎月8万円以上のお金を貯め続けることは簡単なことではありません。
一方で、老後までの時間を活かして資産運用する場合はどうでしょうか。金融庁の資産運用シミュレーターを使って、年間の利回りが3%の場合で試算してみました。すると、毎月の積立額が6万円でも、20年後の資産額は1,970万円になるという結果が出ました。毎月8万円を積み立てて運用した場合なら、2,626万円です。(※手数料・税金は考慮していません。)
このように、資産運用を行ってある程度の利回りを出すことができれば、長い期間続けることで資産額は大きく変わるのです。将来のために貯めるお金を最小限にしながら資産運用で増やしていけたら、今の生活を楽しみながら、将来にも備えられます。これが資産運用の醍醐味といえます。
資産運用のデメリット
資産運用の最大のデメリットは、お金を増やそうとリスクのある金融商品に投資をすると、損失が発生する可能性があることでしょう。そのため投資をする際は、損失が発生する可能性を見越して、手元の資金を全額投入するようなことは避けるのが無難です。また、自分が耐えられないような損失が発生するかもしれないハイリスクな金融商品も避けましょう。
資産運用には、リスクが小さければリターンも小さい、リスクが大きければリターンも大きいという特徴があります。そのため、高い利回りを得たいときはそれ相応のリスクを取る必要があります。しかし、高い利益を狙ってハイリスクな金融商品ばかりで資産運用を行っていると、相場が急変して価格が下落し、お金が必要な時期に資産がぐんと減ってしまう恐れがあります。そうはいっても、預金だけで運用していたらインフレの状況下では現金の価値は目減りしてしまいます。だから、「定期預金で利息をもらって資産運用しています」といっても、十分ではないのです。
「どの金融商品に、いくら投資すれば良い」という決まった正解はありません。自分のライフプランや貯蓄額、リスクに対する耐性、相場など、いろいろな要素を考慮して自分で判断していくことが重要となります。この判断が難しいところも、資産運用のデメリットと言えるでしょう。
資産運用の種類
資産を大きく増やしたいなら、リスクが大きい手段をとることになりますが、今ある資産を減らさず着実に増やしたい部分には、リスクが少ない手段がおすすめです。目的に合わせて資金を色分けし、それぞれの資産運用の手段を選んでください。
なお、資産運用は元本割れのリスクや所定の手数料が発生することがあるため、始める時はそれぞれの金融商品の詳細を確認した上で判断してください。
外貨預金
外貨預金は、外国の通貨建てで預金する資産運用です。金利や為替差益による利益を狙います。低金利下の日本に比べて外国の通貨は金利が高い傾向にあるため、得られる利息が増やしやすいのです。また、為替レートが外国の通貨を買ったときより円安になれば為替差による利益が出ます。ただし、逆に円高になれば、元本割れとなる可能性があります。
代表的な国の為替レートはニュースでも毎日報道されているため、初心者の人でも為替の値動きのイメージは想像しやすいのではないでしょうか。銀行で外貨預金口座を開設すればすぐに始められるので、手軽に始めやすい投資方法といえます。
株式投資
株式投資は、企業が事業資金を集めるために発行する株式を購入する方法です。証券会社に口座を開くと、上場している会社の株式を買うことができます。株式が値上がりしたときに売却すれば利益を得ることができますし、配当金や株主優待が出る企業もあります。
一方で、株価が値下がりしたり、発行した企業が破綻したりといった元本割れのリスクがあります。株価が上がりそうな企業を選定して投資する必要がある点も、初心者にはなかなか難しいところです。一般的にはハイリスク・ハイリターンな投資方法に分類されます。
公社債
国や地方自治体が投資家から資金を借り入れるために発行する債券に投資し、売却したり利子を受け取ったりして利益を得るのが公社債です。債券の価値が下がったり、発行した国や自治体が破綻したりといったことが起これば、元本を割る可能性があります。代表的なものとしては、日本の国債が挙げられます。証券会社や銀行で購入することができます。
発行元が破綻などに陥らなければ、基本的には満期まで約束された利息が受け取れるため、比較的ローリスクな投資方法といえます。あまりリスクを取りたくない資金の投資先に向いています。
投資信託
投資信託は、運用の専門家が株式や債券などに投資をして資金を運用します。投資信託は、商品ごとに様々な投資対象と運用方針が定められています。1つの投資信託を買うだけで、数多くの国や会社に間接的に投資をすることができる点がメリットです。
ただ、株式や公社債に投資をするのと同様に、元本割れする可能性があります。また、リスクや期待できるリターンの大きさは投資信託の商品ごとに大きく異なります。どの投資信託を購入するのかが重要なポイントになります。
資産運用や投資を行う際の注意点
前述の通り、資産運用や投資は必ずしもお金が増えるとは限りません。自分に合った方法を選ぶことが大切です。ここでは特にリスクのある投資を行う場合を想定して、注意点をお伝えします。
目的を明確にする
資産運用では、まず目的をハッキリさせることが大切です。お金を使う時期や必要な金額があいまいなままだと、運用期間や運用金額を決めるのが難しいからです。
目標金額と時期が分かれば、「目標金額÷ゴールまでの月数」を計算することで「毎月貯めるべき金額」が算出できます。貯めたお金を投資に回す場合でも、まずはお金が増えない想定で毎月貯めていくのがおすすめです。なお、もしも目標金額がすでに貯まっている状況であれば、普段の生活で使ってしまわないように、生活費と分けて管理・運用すると良いでしょう。
余剰資金で行う
資産運用の際、リスクのある金融商品に投資するお金については、資産が減ってしまう恐れが伴います。そのため、うまくいかなかったときに困らないよう、余剰資金で行うことを意識しておくと安心です。具体的には「使い道が決まっていないけれど貯まっているお金」「ボーナスなどの臨時収入」「自分が好きに使えるおこづかい」などが挙げられます。
もしくは、「将来レジャーや旅行に使うお金」でも良いでしょう。資産運用がうまくいけば資金にゆとりができて楽しみやすくなりますし、もしも失敗しても普段の生活が困窮するような事態は避けられます。
分散投資を意識する
投資を行う際は、リスクを大きくしすぎないために「分散投資」を意識しましょう。分散投資とは、投資先を1つにしぼらず、複数に分散させることです。「株式と公社債に投資する」といったように値動きが異なる複数の金融商品に投資したり、株式でも複数の銘柄に投資したりすることで、価格が変動するリスクなどを低減させることができます。
例えば、1社の株式だけに全額投資をするとその会社がつぶれてしまうと資産がゼロ円になってしまいます。しかし、投資信託などを使えば容易に100社以上の株式に分散投資をすることができます。「1社が倒産することはそれなりにありそうだけれど、投資した100社以上の会社が全て倒産するような事態はめったにおきないだろう」と想像できると思います。集中投資を避けることで資産が大きく減るリスクを回避できるのが、分散投資のメリットなのです。
長期的な視点で行う
初心者の場合、あまりリスクが高くない方法で、数年や数十年後を見据えた「長期投資」を前提に始めることが大切です。なぜなら、専門知識がなく投資に時間を費やすことも難しい人の場合、常に値動きを追ったり相場を読んだりすることは難しいからです。
長期間資産運用に取り組んでいれば、相場が良い時期が含まれる可能性が高まります。当然相場が悪い時期もあるでしょうが、初めから長期的に取り組むつもりであれば、落ち着いて相場が悪い時期を過ごすことができるのではないでしょうか。
また、相場が悪い時期は投資できる資産の価格が下落しているということですから、「買い時」でもあります。相場が悪い時期はコツコツ投資資産を買い足して過ごし、相場が良い時期をじっくり待つように心がけましょう。日々の値動きに一喜一憂する必要がない点が長期投資のメリットなのです。
専門家に相談する
投資初心者の場合は、専門知識や運用経験が豊富な専門家に相談するのもおすすめです。銀行や証券会社では、無料で相談できるのが一般的です。具体的な金融商品の提案を受けられるので、投資について学びながら投資先を検討することができます。もし金融商品の提案をして欲しくない場合は、商品の販売を行っていない専門家の有料相談を利用するという手もあります。
当然ですが、「誰かに言われるがまま、よくわからないものに手を出す」のはおすすめできません。自分の大切な資産を守り、増やしていくためにも、自分自身が主体的に考え、自分のライフプランに合った資産運用を選ぶことを忘れないでください。
資産運用と投資の違いを理解して資産運用を始めよう
利益を狙ってリスクのある資産へお金を投じる投資と違い、資産運用は預貯金などの安全な方法でお金を増やすことも含まれます。資産運用の目的によっては、預貯金が大半を占める人もいるでしょうし、投資に回す金額のほうが預貯金よりも多くなる人もいるかもしれません。
とはいえ、投資はギャンブルとは異なります。やみくもに運任せでお金を投じるのではなく、長期投資や分散投資を意識したり、専門家を頼ったりしながら、資産が増えそうな金融商品を選ぶことが大切です。その際は、誰かの真似をするのではなく、自分自身のライフプランや投資を行う目的を意識して、投資に回す金額や投資先を決めましょう。
資産運用によって資産が増えれば、将来の生活にゆとりをもたらしてくれます。資産運用は勉強して理解を深めることも大切ですが、実際に資産運用を始めることも重要です。まだ行動に移せていないのであれば、「資産運用するための口座を開設する」「専門家に相談する」「具体的な金融商品の内容を調べて検討する」など、自分が無理なく取り組めそうなことから始めてみてください。
\ ネットでカンタン口座開設 /
SBI新生銀行で今すぐ口座開設

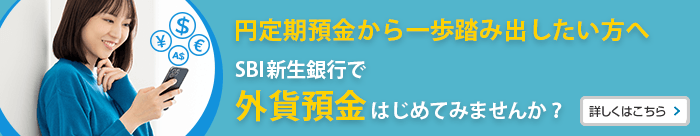


 ポスト
ポスト シェア
シェア LINEで送る
LINEで送る
